あなたの会社の担当者、本当に「税理士」ですか?
実は、税理士事務所の担当者の大半が無資格だという事実は、業界の公然の秘密です。
私もかつては「税理士なんて誰でも同じ」と安易に考えていました。
しかし、ある若手担当者の致命的なミスで役員貸付金が1,500万円になり、今も毎月30万円以上を返済し続ける悪夢を見ています。これは他人事ではありません。
7回税理士を変更した私が、経営者のあなたが絶対に知るべき「無資格職員」の危険な真実と、会社を守るための唯一の方法を、本音で語ります。
【この記事の結論】税理士事務所の担当者は「無資格」が当たり前
| 読者の疑問 | 結論 |
|---|---|
| 担当者は本当に税理士? | 税理士事務所の担当者の大半は「無資格」の職員です。これは業界では常識であり、経営者が陥りがちな誤解です。 |
| 無資格だと何が危険なの? | 知識不足による致命的な経理ミスのリスクがあります。筆者は実際に担当者のミスで1,500万円の役員貸付金を背負いました。 |
| 違法ではないの? | 無資格者が「税務相談」や「税務申告書の最終判断」を行うことは違法です。しかし、補助業務は認められており、見極めが困難です。 |
| どうすれば会社を守れる? | 担当者任せにせず、最終責任者である税理士本人と直接面談し、経営のパートナーとなりうるか相性を見極めることが最も重要です。 |
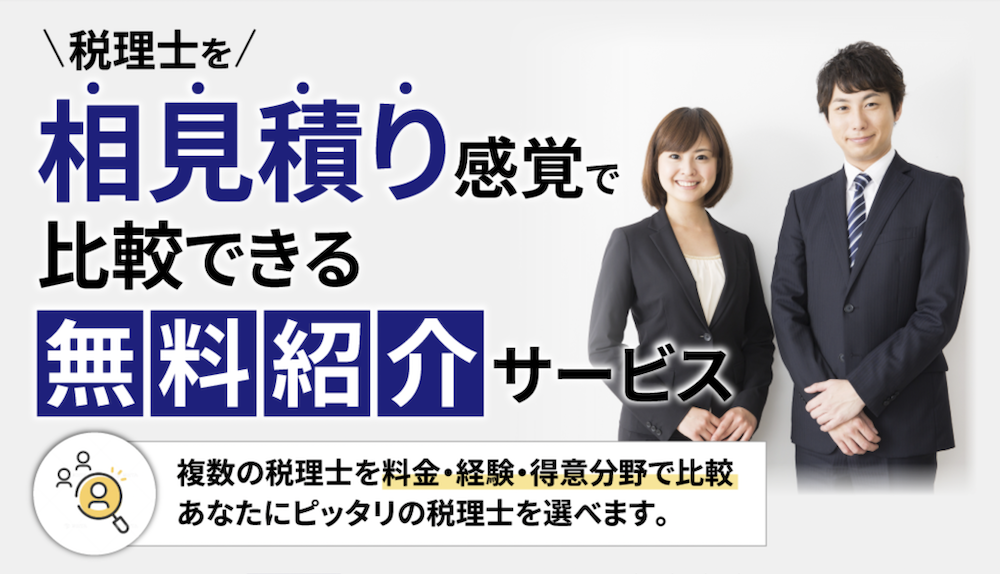
税理士選びで失敗したくない方へ
「税理士ベスト」なら、全国8万人の税理士の中から、あなたの業種・課題・予算に合った税理士を無料で紹介します。
- ✓ 完全無料(追加費用なし)
- ✓ 節税・融資・補助金など専門性で選べる
- ✓ 全国対応・オンライン面談もOK
衝撃の事実!税理士事務所の担当者の大半は「無資格」という現実
「うちの担当者さん、いつもお世話になっています」
経営者であれば、月に一度はこんな会話を交わしているかもしれません。しかし、その担当者が国家資格である「税理士」の資格を持っていないケースがほとんどだとしたら、あなたはどう感じますか?
正直に言うと、私も起業当初はこの事実を知りませんでした。税理士事務所に所属しているのだから、当然みんな税理士資格を持っているのだろう、と。これは経営者が陥りがちな、非常によくある誤解です。
なぜ?「担当者が無資格」が業界の常識になっている理由
私も最初は驚きましたが、これには税理士業界が抱える構造的な問題があります。
深刻な人材不足
税理士試験は合格率が低く、資格取得者が増えにくいのが現状です。特に若手の税理士は少なく、多くの事務所が人材不足に悩んでいます。
コスト構造の問題
税理士資格を持つ職員を雇うと人件費が高くなります。顧問料を抑えるためには、無資格の職員に実務の一部を任せざるを得ないという事務所側の事情もあります。
業務の分業化
会計ソフトの進化により、記帳代行などの単純作業は無資格者でも対応しやすくなりました。そのため、税理士本人は最終チェックや経営判断に関わる部分に集中し、日々の業務は無資格の担当者が行うという分業体制が一般的になっているのです。
このような背景から、「担当者は無資格者、所長が有資格者の税理士」という体制が、業界のスタンダードになってしまっているのが現実です。
無資格でも優秀な担当者はいる?という甘い幻想
もちろん、無資格の担当者の中にも、経験豊富で優秀な方はたくさんいらっしゃいます。私も過去に素晴らしい担当者の方と仕事をした経験はあります。
しかし、その一方で、知識や経験が浅い担当者がいるのも事実です。そして、経営者である我々が、その担当者が「優秀」か「危険」かを見極めるのは、極めて難しいのです。
「若くて親しみやすいから」「レスポンスが早いから」といった理由だけで信頼してしまうと、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。何を隠そう、1,500万円の悪夢を経験した私が、その何よりの証人です。経営者が負うリスクは、あまりにも大きいと言わざるを得ません。
そもそも「無資格職員」とは?税理士法で定められた業務範囲
では、法律上、無資格の職員はどこまでの業務が許されているのでしょうか。この線引きを知っておくことは、自社を守る上で非常に重要です。
税理士法という法律で、税理士にしかできない「独占業務」が厳格に定められています。
無資格職員でも「できること」:記帳代行や資料整理
税理士の独占業務に該当しない、あるいは税理士の監督下で行う補助的な業務は、無資格の職員でも行うことができます。
- 領収書や請求書の整理
- 会計ソフトへのデータ入力(記帳代行)
- 税理士が作成した申告書類の提出代行
- 税理士の指示に基づく資料作成
これらはあくまで「補助業務」であり、税務に関する判断を伴わない作業です。
無資格職員には絶対に「できないこと」:税務相談と判断
一方で、以下の3つは税理士の「独占業務」であり、無資格者が行うことは固く禁じられています。
- 税務代理:納税者に代わって税務申告を行ったり、税務調査の立ち会いをしたりすること。
- 税務書類の作成:確定申告書や法人税申告書など、税務署に提出する書類を作成すること。
- 税務相談:税金の計算や節税方法など、具体的な税務に関する相談に応じること。
特に問題になりやすいのが3つ目の「税務相談」です。日々のやり取りの中で、「この経費は落ちますか?」「こういう節税を考えているのですが…」といった相談に無資格の担当者が答えるのは、厳密には違法行為にあたる可能性があるのです。
これをやったら一発アウト!違法となる具体例
以下のようなケースは、明確な税理士法違反(非税理士による税理士業務の禁止)に該当します。
- 無資格の担当者が、単独の判断で節税策をアドバイスする。
- 無資格の担当者が、最終的な責任者として法人税申告書を作成・完成させる。
- 税務調査の際に、税理士本人が同席せず、無資格の担当者だけで対応する。
これらの違反行為には、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」という厳しい罰則が科せられます。 これは、それだけ専門性の高い判断が求められる業務だということです。
【私の失敗談】無資格担当者のミスで役員貸付金1,500万円…今も続く悪夢
法律の話だけでは、その本当の恐ろしさは伝わらないかもしれません。ここからは、7回税理士を変更した私のキャリアで最大の失敗談をお話しします。これは、無資格(あるいは知識不足)の担当者を安易に信じた結果、私の会社が今も苦しみ続けている生々しい記録です。
「若くて親しみやすい」が落とし穴だった2人目の税理士
創業から2年目、法人化を機に私は2人目の税理士と契約しました。知人の紹介だった最初の税理士が典型的な「安かろう悪かろう」だったため、次はしっかりコミュニケーションが取れる人がいいと考え、30代の若手税理士事務所を選びました。
担当になったのは、同年代の親しみやすい男性職員。レスポンスも早く、チャットで気軽に相談できる関係性に、私は「今度は当たりだ」とすっかり安心していました。彼が税理士資格を持っていないことなど、当時は気にも留めていませんでした。
なぜ1,500万円もの役員貸付金が発生したのか?
悲劇は、静かに、しかし確実に進行していました。
当時の私は、会社の経費を個人のクレジットカードで立て替えたり、会社の普通預金から直接経費を支払ったりすることが頻繁にありました。これは多くの中小企業経営者がやっていることだと思います。
問題は、その経理処理でした。担当者は、私が立て替えた経費の精算処理を誤り、さらに、会社の通帳から支払われた経費の一部を「社長個人への貸付金」として処理し続けていたのです。
つまり、会社のために使ったお金が、すべて「社長が会社から借りたお金」にすり替わっていたのです。月次の報告は受けていましたが、私も当時は会計知識に乏しく、この致命的なミスに全く気づけませんでした。
ミスの発覚、そして税理士の無責任な対応
ミスが発覚したのは、契約から3年近くが経ち、銀行融資の相談で決算書を詳しく見ていた時でした。B/S(貸借対照表)に「役員貸付金 1,500万円」という、ありえない勘定科目が計上されているのを見つけたのです。
血の気が引きました。すぐに担当者に説明を求めましたが、彼の答えは曖昧で、要領を得ません。最終的に代表税理士が出てきましたが、彼の口から出たのは謝罪ではなく、「処理方法については双方の認識の齟齬があった」「今から修正するのは難しい」という信じられない言葉でした。
法律上、職員のミスは雇用主である税理士の「使用者責任」が問われます。 しかし、それを証明し、損害賠償を請求するには膨大な時間と労力がかかります。結局、私は泣き寝入りするしかありませんでした。この時、「税理士はパートナーなどではない。自分の会社は自分で守るしかない」と骨身に染みて理解したのです。
毎月30万円の返済…キャッシュフローを破壊する時限爆弾
この1,500万円の役員貸付金は、今も私の会社の経営に重くのしかかっています。
銀行は役員貸付金を「使途不明金」と見なし、融資に極めて消極的になります。決算書の見栄えも最悪です。
何より深刻なのは、この架空の借金を解消するために、私は今も毎月30万円以上を役員報酬から会社に「返済」し続けていることです。実際には1円も借りていないにもかかわらず、です。これは会社のキャッシュフローを直接的に破壊する、まさに時限爆弾です。年間360万円以上のお金が、たった一人の担当者のミスのせいで消えていく。この悪夢は、まだ終わっていません。
あなたの担当者は大丈夫?危険な「無資格担当者」を見抜く5つのチェックリスト
私のようにならないために、経営者は自衛するしかありません。今の担当者が本当に信頼できるのか、以下の5つのポイントで冷静にチェックしてみてください。
1. 税理士バッジをつけているか、税理士証票を提示できるか?
最も簡単で確実な方法です。税理士は、桜の花びらの中央に「日」の字が入ったデザインのバッジを携行しています。 また、顔写真付きの「税理士証票」というカードも持っています。
初回の面談時や、少しでも疑問に思ったら、「失礼ですが、税理士証票を拝見できますか?」と尋ねてみましょう。これは経営者として当然の権利です。誠実な事務所であれば、快く応じてくれるはずです。
2. 質問に対して「持ち帰って確認します」が多くないか?
税務に関する質問をした際に、「一旦持ち帰って、先生に確認してから回答します」という返答が頻繁にある場合、その担当者自身に十分な知識がない可能性があります。もちろん、複雑な案件や最新の税制改正に関する内容であれば、慎重を期すために持ち帰るのは当然です。しかし、基本的な質問にさえ即答できない場合は注意が必要です。
3. デメリットやリスクを説明してくれるか?
「この節税策を使えば、これだけ税金が安くなりますよ」とメリットばかりを強調してくる担当者には警戒が必要です。本当に優秀な担当者は、節税提案とセットで、必ずその手法に伴う税務調査のリスクやデメリットを説明してくれます。
これは私の4人目の税理士選びの失敗から学んだ教訓でもあります。リスク管理の視点があるかどうかは、プロフェッショナルを見極める重要なポイントです。
4. 最終的な判断を「先生に確認します」と先延ばしにしていないか?
質問への回答だけでなく、申告内容の最終確認など、重要な判断をすべて「先生(所長税理士)に確認します」と言って先延ばしにする担当者も要注意です。これは、事務所内の監督体制が機能している証拠とも言えますが、一方で担当者自身に判断能力が全くない可能性も示唆しています。これでは、スピーディーな経営判断は望めません。
5. 契約書で「担当者は有資格者に限る」と明記できるか?
契約段階でのリスクヘッジとして、顧問契約書に「担当者は税理士有資格者とする」という一文を加えられるか交渉してみるのも一つの手です。もちろん、業界の慣習から難しい場合も多いでしょう。
しかし、この要望に対して「なぜですか?」と不審な顔をしたり、頑なに拒否したりする事務所は、何か隠したいことがあるのかもしれません。少なくとも、担当者の資格についてオープンに話せない事務所は避けるべきだと私は考えます。
無資格担当者で後悔しない!7回税理士を変えた私が行き着いた「本物のパートナー」の選び方
では、どうすれば私の1,500万円のような失敗を避け、本当に信頼できる税理士に出会えるのでしょうか。7回の変更を経て私が行き着いた結論は、非常にシンプルです。
「安さ」や「紹介」だけで選ぶのは絶対にやめる
私の最初の失敗は、「安ければいい」という考えでした。2回目の失敗は、「若くて親しみやすい」という安易な安心感でした。どちらも、経営の根幹を支えるパートナー選びとしては、あまりに稚拙だったと反省しています。
また、知人の紹介が必ずしも良いとは限りません。その知人の会社とあなたの会社では、事業フェーズも規模も、求めるサービスも全く違うからです。「紹介だから断りづらい」という関係性は、後々のトラブルの元になります。
料金だけでなく「サービス内容」と「責任の所在」を明確にする
顧問契約を結ぶ前に、必ず以下の点を確認してください。
- 業務範囲: 月次顧問料には、どこまでのサービスが含まれているのか?(記帳代行、月次面談、決算申告、年末調整など)
- 責任体制: ミスが発生した場合、どのような補償体制になっているのか?(税理士賠償責任保険への加入状況など)
- 連絡体制: 担当者は誰で、最終責任者である税理士本人とはどのくらいの頻度で話せるのか?
これらの内容を書面(契約書)で明確にしておくことが、後々の「言った・言わない」を防ぐ唯一の方法です。
経営者の視点で「未来の話」ができる税理士を選ぶ
私が今の8人目の税理士に満足している最大の理由は、彼が「過去の数字」を処理するだけでなく、その数字を元に「会社の未来の話」をしてくれるからです。
「この事業の利益率が良いので、来期はここに投資を集中させましょう」
「3ヶ月後にキャッシュが厳しくなりそうなので、早めに融資の準備を始めましょう」
このように、経営者の視点に立って、未来の成長やリスクについて一緒に考えてくれる存在。これこそが、単なる外注先と「経営のパートナー」を分ける決定的な違いです。
最終結論:税理士本人との面談と相性がすべて
担当者が有資格者か無資格か。それも重要ですが、突き詰めれば、最終的な責任者である所長税理士本人と直接会い、経営に対する考え方や価値観が合うかどうか。すべてはこれに尽きます。
あなたの会社の未来を、この人に任せられるか。あなたの孤独な決断に、寄り添ってくれるか。面談でそういった「相性」を確かめること以上に重要なことはありません。
よくある質問(FAQ)
Q: 税理士事務所の担当者が無資格なのは、違法ではないのですか?
A: 無資格の職員がいること自体は違法ではありません。ただし、税理士の独占業務である「税務相談」や「税務申告書の作成・最終判断」を無資格者が行うことは税理士法違反となります。重要なのは、税理士本人の適切な監督下で業務が行われているかという点です。
Q: 担当者のミスで損害が出た場合、誰が責任を取るのですか?
A: 法律上、職員のミスは雇用主である税理士の責任となります(使用者責任)。しかし、私の経験上、責任を認めず争いになったり、結局泣き寝入りになったりするケースも少なくありません。損害賠償請求には多大な労力がかかるため、ミスをしない信頼できる税理士を選ぶことが何より重要です。
Q: 担当者がコロコロ変わるのですが、問題ありますか?
A: 問題です。担当者が頻繁に変わる事務所は、労働環境に問題があるか、顧客対応を軽視している可能性があります。会社の状況を深く理解してもらえず、一貫したアドバイスを受けられないリスクがあります。私も大手税理士法人で同様の経験をしました。
Q: 担当者が無資格かどうか、どうやって確認すればいいですか?
A: 最も確実なのは、面談時に「失礼ですが、税理士証票を拝見できますか?」と直接尋ねることです。また、日本税理士会連合会のウェブサイトで名前を検索することも可能です。誠実な税理士であれば、この質問を不快に思うことはありません。
Q: 今の担当者が無資格で不安です。すぐに税理士を変更すべきですか?
A: まずは代表税理士に面談を求め、今後の担当体制や業務の監督方法について直接確認しましょう。その上で不安が解消されない、あるいは不誠実な対応をされた場合は、変更を検討すべきです。私の経験上、不安を抱えたまま付き合い続けるのは精神的にも経営的にもマイナスです。
まとめ
税理士事務所の担当者が無資格であることは珍しくありませんが、その裏に潜むリスクは経営を揺るがすほど大きいものです。
私の1,500万円の失敗談は、その氷山の一角に過ぎません。
担当者が有資格者か無資格かという点だけでなく、最終責任者である税理士本人が、あなたの会社の未来を真剣に考える「パートナー」となりうる人物かを見極めることが最も重要です。
もう、税理士選びで失敗する経営者を一人でも減らしたい。この記事が、あなたの会社を守る一助となれば幸いです。
そうだ、税理士を変えよう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✓ 私が7回も税理士を変更した理由、それは…
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税理士選びで失敗すると、年間数百万円のキャッシュを失います。
私自身、2社目の税理士の経理処理ミスで役員貸付金1,500万円が発生し、
今も毎月30万円以上を返済し続けています。
でも、7社目の税理士に出会ってから、年間350万円のキャッシュが残るようになりました。
「税理士を変えたいけど、どうやって探せばいいかわからない…」
そんなあなたに、私が実際に利用した税理士紹介サービス「税理士ベスト」をおすすめします。
私のような失敗をしないために、まずは無料で相談してみてください。
税理士を変えるだけで、会社が変わる
全国8万人の中から、あなたにピッタリの税理士を無料で紹介
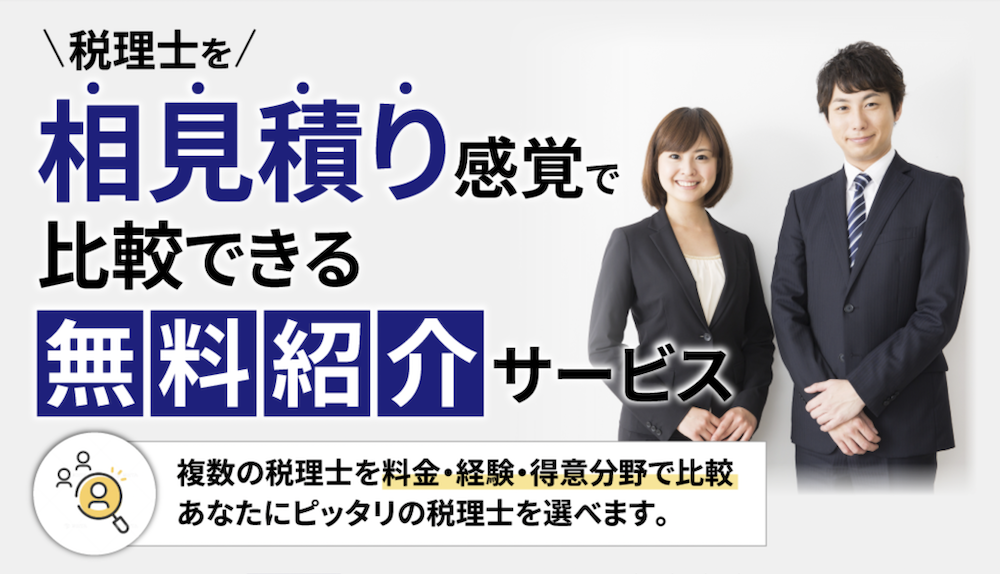
- ✓ 完全無料で税理士を紹介
- ✓ 節税・融資・補助金など、専門性で選べる
- ✓ 面談後に「合わない」と思ったら、別の税理士を再紹介
※完全無料・追加費用なし



